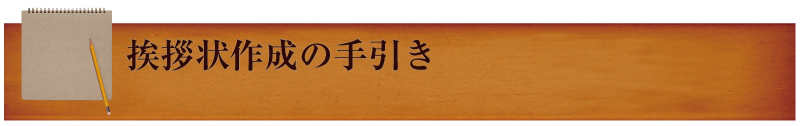満中陰(志)について
仏教では、人が死んでからの49日間を、死者が生と死・陰と陽の狭間に居ると考えられ、その期間を「中陰」もしくは「中有」と呼ばれます。
日本では死後、死者は魂を清めて仏になる為に中陰「中有」の道を歩くと考えられ、
その期間中の49日間(中陰・中有)を、下記の7日毎に遺族が中陰法要を行います。
亡くなった日が月の後半の場合、「大練忌」が次々月になることがあります。
これを「三月越(みつきごし)」と呼び、「49日の三月またぎ」と称して”中陰(49日)が
足かけ3ヶ月に渡ってはいけない”と考えられ、「小練忌」に大練忌の法要を行い忌中明けとするという地域もあります。
中陰法要
・初七日(しょなのか)…「初願忌」(しょがんき)
・二七日(ふたなのか)…「以芳忌」(いほうき)
・三七日(みなのか)…「洒水忌」(しゃすいき)
・四七日(よなのか)…「阿経忌」(あぎょうき)
・初月忌(しょがっき)(立日)…没後、最初の月命日
・五七日(いつなのか)…「小練忌」(しょうれんき)
・六七日(むなのか)…「檀弘忌」(だんこうき)
・七七日(なななのか)四十九日・満中陰・尽七日…「大練忌(だいれんき)」
*臨終の日を含め、数えて50日目が「忌明け」、「忌明(きめい)」と呼ばれます。
満中陰志
満中陰志とは、忌明け法要の後、喪家より出席者や香典を頂いた先様に対して贈る
お礼の品のことで、特に西日本地区で多く用いられるものです。
「志」とは、謝意を表す言葉で、「お蔭様で無事満中陰を迎えました」という
感謝の気持ちを表し、無事に忌明けを終えた報告と、頂いた香典に対するお礼の
挨拶状を添えてお返しをお送りするのが一般的なマナーとされています。